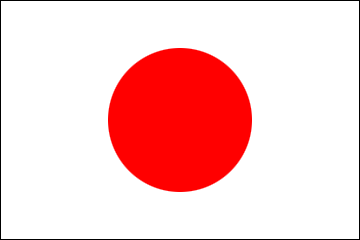二国間関係 - 移住史
令和3年6月22日
移住の開始
パラグアイへの日本人移住の歴史は、1936年5月15日に始まります。他のラテンアメリカ諸国と比べると、比較的新しいと言えるでしょう(メキシコでは1897年、ペルーでは1899年、ブラジルでは1908年に移住開始)。1934年、ブラ ジル政府は、新規移住を制限する法律を公布したため、同年、ブラジル拓殖組合の宮坂国人専務理事が、日本人入植のための調査をパラグアイで初めて実施しました。翌1935年、日本政府は詳細を把握すべく調査団をパラグアイに派遣し、最終的に、アスンシオンから南東約130kmにある現在ラ・コルメナと名付けられている土地を購入することを決定、1936年4月にパラグアイ政府は、ブラジル拓殖組合に対し、日本人移民100家族を受け入れる許可を出しました。
ブラジル拓殖組合は、土地約11,000haを購入し、ラ・コルメナ移住地を形成しました。同年5月25日、ブラジルで入植経験がある4家族33名の日本人が、新しい移民を指導する目的で、ラ・コルメナ移住地に到着、その後さらに4家族36名が到着しました。1936年8月12日、11家族81名が、日本から最初のパラグアイ移民として到着、第2次世界大戦により日本人移住が途絶える1941年まで、計123家族790人が入植しました。
入植者は、熱帯林を切り開き、綿花、柑橘類、米、サトウキビなどの農作物を栽培すべく、耕地を準備しましたが、インフラの未整備、特に道路不足が、農作物を商品化する上で大きな障害となっていました。
ブラジル拓殖組合は、土地約11,000haを購入し、ラ・コルメナ移住地を形成しました。同年5月25日、ブラジルで入植経験がある4家族33名の日本人が、新しい移民を指導する目的で、ラ・コルメナ移住地に到着、その後さらに4家族36名が到着しました。1936年8月12日、11家族81名が、日本から最初のパラグアイ移民として到着、第2次世界大戦により日本人移住が途絶える1941年まで、計123家族790人が入植しました。
入植者は、熱帯林を切り開き、綿花、柑橘類、米、サトウキビなどの農作物を栽培すべく、耕地を準備しましたが、インフラの未整備、特に道路不足が、農作物を商品化する上で大きな障害となっていました。
1952年に到着した新移民
第2次世界大戦後、パラグアイ政府がブラジル拓殖組合に移住許可を出したため、日本人移住は1952年に再開され、ラ・コルメナ移住地に18名が入植しました。同年、パラグアイ政府は、パラグアイ南部の開発のため、イタプア県に新たにチャベス移住地を創設、入植を許可しました。これにより、35家族210名の日本人が入植しましたが、増加する日本人移住者に対してチャベス移住地の土地が不足する事態となったため、1955年に同県のフラム移住地への入植を開始、その後、1956年にフジ移住地、1957年にラ・パス移住地、サンタ・ロサ移住地にまで拡大しました。
一方、1956年には、CAFE(Compañía Americana de Fomento Económico)農園への契約雇用農(コーヒー栽培)として、アマンバイ県に137家族の日本人が入植しました。しかし、その3年後、同社は倒産したため、アマンバイ移住地の入植者は他の農作物の生産や商業に従事することになります。
1959年、日本・パラグアイ両国政府は、「日本・パラグアイ移住協定」を締結し、以降30年間に亘って85,000名の日本人移住者の受入が決定されました。1960年、JICAは、現在のイタプア県ピラポ地区に土地を購入し、26家族が入植したほか、アルト・パラナ県イグアス地区に約87,000haの土地を購入しました。イグアス移住地は、パラグアイで最も日本人移住者の多い移住地となっています。
現在は、推定約1万人の日本人移住者及び日系人がパラグアイに居住しています。都市部で商工業に従事する移住者もいますが、多くの移住者は主に移住地で農業を営んでいます。
一方、1956年には、CAFE(Compañía Americana de Fomento Económico)農園への契約雇用農(コーヒー栽培)として、アマンバイ県に137家族の日本人が入植しました。しかし、その3年後、同社は倒産したため、アマンバイ移住地の入植者は他の農作物の生産や商業に従事することになります。
1959年、日本・パラグアイ両国政府は、「日本・パラグアイ移住協定」を締結し、以降30年間に亘って85,000名の日本人移住者の受入が決定されました。1960年、JICAは、現在のイタプア県ピラポ地区に土地を購入し、26家族が入植したほか、アルト・パラナ県イグアス地区に約87,000haの土地を購入しました。イグアス移住地は、パラグアイで最も日本人移住者の多い移住地となっています。
現在は、推定約1万人の日本人移住者及び日系人がパラグアイに居住しています。都市部で商工業に従事する移住者もいますが、多くの移住者は主に移住地で農業を営んでいます。
パラグアイ経済への貢献
農業に従事している日本人移住者は、パラグアイの経済活動人口のうち農業従事者の約1%に相当しますが、大豆に関しては全国生産量の2.3%(2006年)、小麦に至っては7%(2007年)を生産しています。地方に居住する移住者の活動は、蔬菜類、穀物、柑橘類などの短期作物・長期作物の生産や養鶏など、様々です。
移住者によるトマト、大豆、小麦及び卵の生産は、パラグアイの農業に大きな影響を与えましたが、日本人移住者の農業活動により大豆の輸出に道筋が付けられたことは、あまり知られていません。
チャベス移住地、フラム移住地に入植した移住者は、当初、近隣のドイツ人移住者の農業を模範とし、短期作物であるトウモロコシ、長期作物である油桐やマテ(茶葉)を栽培していましたが、当時の農産物価格は非常に低く、商業化は必ずしも上手くいきませんでした。経済的に厳しくなっていく中、日本から持ってきた大豆の種子で、わずかながらも自給自足用に大豆の栽培を始めた移住者がいました。この大豆が豊作となったことに農協は注目し、農協は大豆を移住者の主要農作物として輸出する方法を検討し始めたのです。1959年2月、イタプア県農協会を構成するチャベス、フジ、ラパス、サンタロサの4移住地の農協が協議を行い、その後、大豆輸出が開始されたことで、パラグアイ産大豆が注目を浴びるようになりました。
移住者によるトマト、大豆、小麦及び卵の生産は、パラグアイの農業に大きな影響を与えましたが、日本人移住者の農業活動により大豆の輸出に道筋が付けられたことは、あまり知られていません。
チャベス移住地、フラム移住地に入植した移住者は、当初、近隣のドイツ人移住者の農業を模範とし、短期作物であるトウモロコシ、長期作物である油桐やマテ(茶葉)を栽培していましたが、当時の農産物価格は非常に低く、商業化は必ずしも上手くいきませんでした。経済的に厳しくなっていく中、日本から持ってきた大豆の種子で、わずかながらも自給自足用に大豆の栽培を始めた移住者がいました。この大豆が豊作となったことに農協は注目し、農協は大豆を移住者の主要農作物として輸出する方法を検討し始めたのです。1959年2月、イタプア県農協会を構成するチャベス、フジ、ラパス、サンタロサの4移住地の農協が協議を行い、その後、大豆輸出が開始されたことで、パラグアイ産大豆が注目を浴びるようになりました。
日本の協力
我が国政府とJICAは協力して、パラグアイの大豆生産増加に向けて取り組んできました。
我が国政府は、パラグアイの土地に適合した新種の大豆を開発すべく、CRIA(Centro Regional de Investigación Agrícola、地域農業研究センター)、CEMA(Centro de Mecanización Agrícola、農業機械化センター)、CEDEFO(Centro de Desarrollo Forestal、林業開発訓練センター)をイタプア県に建設したほか、生産・商業化促進のため、道路整備や電化などあらゆるプロジェクトを実施しました。
JICAは、大豆の改良品種を導入したほか、専門家派遣や、研究・栽培に必要な機材の供与を行いました。JICAが行った技術協力で最も重要なのは、不耕起栽培技術の導入・普及への貢献です。これにより、土地浸食の防止、コストの最小化、生産量増加を達成でき、農業技術に革命的な変化がもたらされました。今日、大豆は、パラグアイの主要輸出作物の一つとして、また、パラグアイにとって重要な外貨獲得手段として、成長を続けています。
我が国政府は、パラグアイの土地に適合した新種の大豆を開発すべく、CRIA(Centro Regional de Investigación Agrícola、地域農業研究センター)、CEMA(Centro de Mecanización Agrícola、農業機械化センター)、CEDEFO(Centro de Desarrollo Forestal、林業開発訓練センター)をイタプア県に建設したほか、生産・商業化促進のため、道路整備や電化などあらゆるプロジェクトを実施しました。
JICAは、大豆の改良品種を導入したほか、専門家派遣や、研究・栽培に必要な機材の供与を行いました。JICAが行った技術協力で最も重要なのは、不耕起栽培技術の導入・普及への貢献です。これにより、土地浸食の防止、コストの最小化、生産量増加を達成でき、農業技術に革命的な変化がもたらされました。今日、大豆は、パラグアイの主要輸出作物の一つとして、また、パラグアイにとって重要な外貨獲得手段として、成長を続けています。